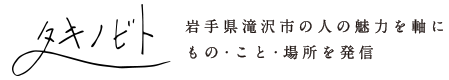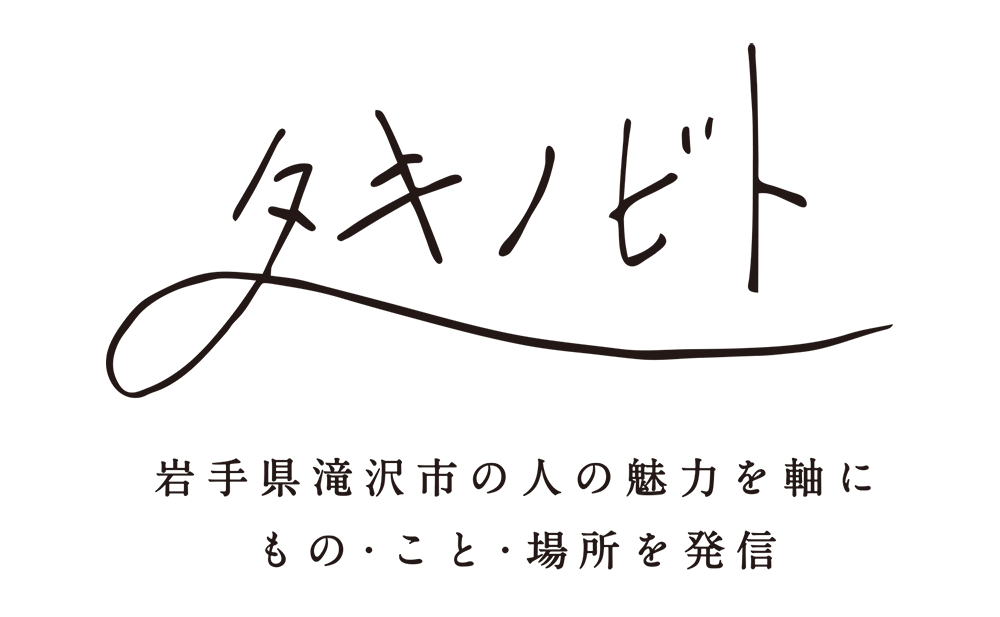若き匠が切り開く南部鉄器の新しい時代 〜タヤマスタジオ株式会社代表取締役 田山貴紘さん〜

伝統工芸を扱う工房としては一風変わった社名の「タヤマスタジオ」。そこには、伝統を大切に守りながらも、南部鉄器の枠からはみだそうとする強い意志を感じる。一人の職人として技術を追求する一方で、若い職人を抱える経営者でもある田山貴紘さん。南部鉄器が身近な存在でありながら、一度は故郷滝沢市を離れた田山さんが、ふたたび南部鉄器という伝統工芸に向き合うことになった心の変化を辿ってみた。
外から見た岩手、ありきたりなものが実はそうではなかった

「南部鉄器に対しては、たぶん、一般の若者と同じくらいの感覚でしかなかったと思いますね。実はそんなに南部鉄器を知らないし、かっこいいともあまり思っていなかった」。10代の頃の心境をそう語る田山さん。父親は南部鉄器の職人だが、社会科で少し習うくらいの一般的な南部鉄器の印象しかなかったという。生まれ育った滝沢市についても、「愛着っていうのは正直そんなになかったです。地元を離れるときにも感傷的なものはなかった」
そして進学のため、地元を離れた。「関東に出てみると、中から見た岩手ではなくて、外から見た岩手になりますよね。それを実感として感じる機会がやっぱりあって、たとえば食事とか。刺身とか寿司、焼き魚なんかは、東京で食べるとあまり美味しくなかった。生活の中にあったありきたりなものが、実は当たり前じゃなかった、そういうことが徐々に実感として分かり始める経験をしたのは、やはり岩手を出たからだと思うんですね」
埼玉大学大学院を卒業後、全国に支店を持つ食品メーカーに就職。営業担当者として、仕事に忙殺される日々が続いたという。「自分にとってのキャリアアップというのは意識していたので、営業の仕事をしながら社会情勢や、もちろん売るということに関するマーケティング的な専門知識とか様々な勉強をしました。人として分厚い人間になるために青年塾という塾にも通いました」
上昇志向が強い田山さん。社内における重要ポストを目指す気持ちもあり、20代中盤までは、滝沢、南部鉄器といったキーワードは頭の中にはなく、地元に対して特別な思いを寄せることは全くなかったのだとか。
自分の持っている知識、ノウハウ、周りにあるもの全てを棚卸して、
どういう方向に進もうか悶々と考えていた
20代前半と後半とでは、ガラッと価値観が変わったという。「就職先での新入社員研修の内容が、とにかく本を読めっていう内容だったんですよね。1000円とか2000円で、その人が人生で経験したことがいっぱい書いてあると。僕は本を読むのが大っ嫌いだったんですよ。でも、それから月10冊以上は読むと決めてやり始めました」
読書から学んだことの一つを語ってくれた。「人生って3万日くらい。3万回寝たら死んでしまう。3万日をどう過ごすかって考えると、意外と短いと思ったんですよ。いろんな事をやろうとしてもできないし、死んでしまったらおしまいだし。だから、基本的に自分のやりたいことをやるのが楽しいんだろうなって思うきっかけになりました。死ぬ間際に後悔するくらいなら、失敗してでもやりたい事をやったほうが、たぶん幸せなんだろうなって」
田山さんの語る自分のやりたいこと、自分にとって楽しいことというのは、決して自分本位なものではなく、志があった。
自分のやりたい事をやる
自分が死んだ先のことを考えながらやる
それが志だと知った

「自分が良いと思うことをやるのが第一だと思うんですけど、その先に余力があれば、自分が死んだ後に喜ばれたり、残ることをやりたいと思いました。欲望って小さいと害にしかならないけど、すごく大きいとすごく世の中の為になるっていうことを学んで、自分の好きな方向に進もうっていう気持ちが湧いてきたんです」
20代後半に差し掛かった頃、これから30代を向かえるにあたって自分はどういった方向で人生を歩んでいくのかを徐々に考えはじめ、具体化していこうと思ったという。
「学生までは、用意されたレールの上でただただ頑張るといった状況だったんですけど、社会人になると世の中がどういう力学で動いているのかが分かり始めたんですね。自分の思う理想と、社会の仕組みの乖離っていうのが見え始めてきたんです。その中で自分がどう動いていくか、自分を含めて、関わる人たちにとってどうするのがいいのか、そんな事を考え出したのが20代後半だったんですよね」
自分自身の将来の在り方について考える日々の中で、転機が訪れる。
2011年3月11日、東日本大震災。
「自分にしかできないことは何かっていうのが、軸にありました。自分の持っている営業ノウハウなんて、他にも持っている人はいっぱいいますし。僕にしかできないものを探していくと、地元に対する何かとか、南部鉄器っていう伝統文化に関わることっていうのが、以外とすぐに大きくなってきました」
伝統とか、地元で受け継がれて、繋がってきているものに価値がある
「大きな資本を元手に南部鉄器の伝統を作ろうと思っても、不可能なんですよね。地元にある価値って、地元に根付いているもの、過去から今に繋がってきているものだったりするから。それって、お金をいくら出しても買えないんですよね」
そう話す田山さんの母方の祖父は、ユネスコの無形文化遺産にも指定されている早池峰神楽の元長老。祖父が亡くなった時、祖父だけしか知らない幾つかの舞が世の中から失われたのだとか。
「室町時代からあると言われている早池峰神楽の伝承と伝統が、いくつかそこで途絶えているんですよね。過去から繋がってきているものに価値を覚え始めた時に、残念だな、もったいないなっていう気持ちが湧いてきたんですね」
2012年、29歳の時に故郷滝沢市に帰郷。田山鐵瓶工房にて、父親である和康さんのもと職人としての修行が始まる。翌2013年にはタヤマスタジオ株式会社を設立。
お客さんのことを思う気持ちは、結局自分たちに帰ってくる
「僕らは物を作っているんですけど、その物には実は有形じゃなくて、無形の伝統も入っているんですよ」と話す田山さん。鉄瓶に込められている心について教えてくれた。
「例えばお茶の世界。主人が客人にお茶を振る舞う、おもてなしをするっていうのがお茶の世界なんですけど、右手で鉄瓶を持った時に、客人に見える側が表、自分に見える側が裏なんです。表に華美な装飾を施して、裏は落ち着いた感じになっているんですね。そういった心が南部鉄器に入っているんです。これは、お客さんに対する思いやりがないとできない。それをもし僕らが忘れたら、ただのもの作りになってしまう。大量生産、大量消費という効率化の中で置いてきてしまった大切なもの、重要な事が入っている気がするんです」
職人としての仕事に終わりはない 技術追求は死ぬまで修行
そういうところが人生としてすごく面白い

技術的な部分については、果てしなく課題があるという。「いかに平面に立体感のある模様をつけるかとか、今の人に受け入れられやすいデザインってどんなもので、それを物として実現するにはどうしたら良いのかっていう事とか」工芸品に求められる技術の難しさについて語る田山さん。植物や動物の模様をつける為には絵画の技術も求められるというから、追求すべき技術は果てしないものになるそうだ。そういった難しさが、南部鉄器の奥深さや、面白さにも繋がっているようだ。
江戸時代に盛岡藩が築城して町を作る時に、鉄を扱う技術が必要だったことから職人が集められ、それが今に繋がっているのが南部鉄器なのだとか。「紐解くと時間的な深さが相当あって、その時に携わっていた人の繋がりが今に至るので、価値がありすぎる。それをどうビジネスに繋げていけるように職人を育てるかっていうのが、今の視点になってきているんです」と田山さん。過去の自分と現在の自分とでは、南部鉄器というキーワードから発想することが全く異なるので、すごく面白いという。
日本の文化に根付いた技術であったり、地域性であったりするのは、それ自体が差別化されたものだという。「世界で勝負する時には小規模でもめちゃめちゃ面白い」と、世界を相手にビジネスを展開していくことも視野に入れているようだ。
ここに住んでいる僕たちが普通だなと思うところに価値がある
「春になると田んぼに水を入れる為に水路に水が流れる。そんな風景もきらきらしているんですよね。冬になれば空気が澄んでいて岩手山が綺麗に見えるし、都会だと普通じゃないところにすごく価値があるなって思ったのは、地元に帰ってきてからですね」つづけて、生まれ育った滝沢への思いを話してくれた。
「新しい価値って、たぶん沢山転がっているんですよね。それが見えるかどうかってすごく大事だなって思うんですよね。長年住んでいると意外と見えなくなってしまうことが多いと思うけど、僕は一度外に出ているので、多少は見えるかなっていう気はします。いっぱい転がっていると思いますよ」
僕ら大人がいかに滝沢を楽しい場所にしていくか
滝沢市の未来を担う若い世代に向けて、田山さんが思うことを話してもらった。
「大人である僕らが、いかに楽しんで仕事をするかっていうのが、一番大切だと思うんですね。それが結果的に子供たちの目から見て“滝沢っていいよね”っていうことに繋がると思う。いくら若い人たちに言葉で言っても嘘をついていることになってしまうので」そして、次のようにつづけた。
「若い時って、今やっていることが将来どう自分に良いかってわからない。若い人たちには、変だなとか、憤りとか、生きづらさとか、疑問とか、抑えられがちなそういったことを大切にしてほしい。その中に結構答えがある気がするので」
田山さん自身が20代のころに自分の将来について悶々と考えて、答えを探していたからこそ出てくる言葉のように思える。
苦しい時ほど、仕事は楽しい

「最近は苦しんで、もがいている時が楽しいですね」そう話す理由は、苦しい経験の後には、ちょっと成長していることが実感できて、その成長が約束されているような気がするからだという。「逆に苦しいことをしていない時っていうのは、やっぱりさぼっている時かな。ある程度苦しいなって思うと、最初は苦しいんですけど、それを噛みしめていくと、また一つ大きくなるぞって思えてすごく面白い。筋トレと同じような感じ。自分で自分をいじめるって、AIじゃできないだろうなって(笑)」
目の前のことを苦しいけどやり続けるというのは、若い人に対してだけでなく、すべての大人に向けても届けたいメッセージのようだ。
最後に、これから目指していきたい未来像について聞いた。
「やっぱり自分が楽しむっていうことを中心に据えたい」という。「そこに一緒に携わりたいという人が集まってきて、結果的にそれが価値になっていけるように努力したい」。地域における雇用の創出ということも念頭においているという。
一流を目指す一人の職人として、また南部鉄器の世界を背負っていくことになるであろう一人の経営者として、田山さんの挑戦はまだまだ始まったばかりだ。